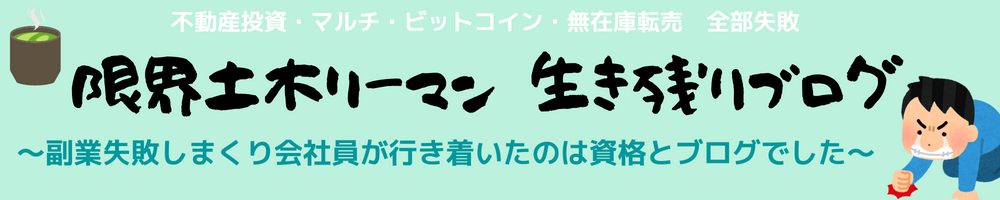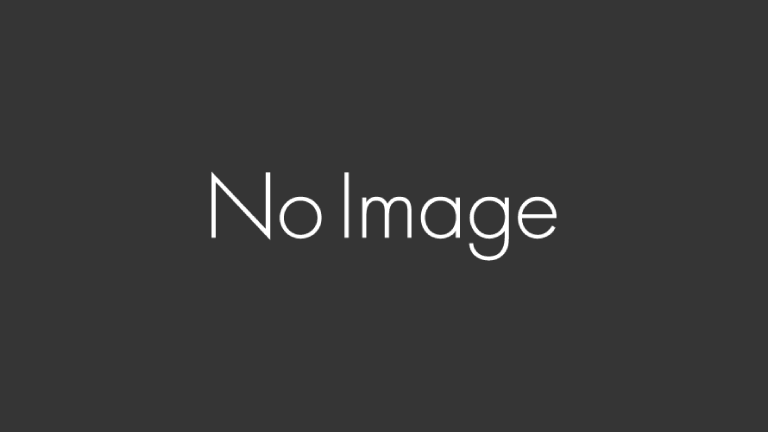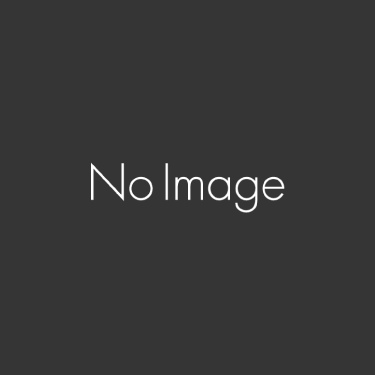コンクリート診断士に一発合格を果たし、私は未経験分野ではありましたが、橋梁補修工事の施工管理を4年間やってこれました。
県内でもマンモス市役所の方からは認知されるようになり、一番詳しい人として言ってもらえるほどになったことは今年いちばん嬉しかったことです。
さて、建設業における資格は、基本的には何かをこなすための要件になっていることがほとんどです。
要件を満たすために資格を取得する。それが自然な流れですよね。
しかし、コンクリート診断士は要件になるケースは非常に少ないです。ただ、『コンクリート診断士』、『技術士補』、『二級土木施工管理技士』を所有している私からすると最も実務において役立った資格だと感じています。
こんな人におすすめ
・コンクリート診断士を取得したらどういうメリットが得られるのか?
・補修系の知識をつけるためにコンクリート診断士の受験を検討している
まず、皆さんはコンクリート診断士はどういう資格かご存知でしょうか?
コンクリート診断士とは?
コンクリート診断士を取得することにおけるいちばんのメリットは、『診断における応用力が身につく』ことです。
知識面を網羅的に頭に叩き込まないと合格することはできないことはもちろんのことですが、コンクリート診断士の肝は論文です。
出題傾向はあるものの、施工管理技士のように、出題内容を予想できるものではなく、現場状況や構造物の損傷程度を資料から読み解き、その場で診断プランを思考することが求められています。
そのため、頭を抱えて、どういう経緯を経て、損傷発生に至っているのか?その原因に対する適切な対応策は何なのかをよく考えなければなりません。
なので、試験勉強をしていく中で、構造物と損傷が明らかになっている問題文に対して、どうしてその損傷が発生したのか?発生原因を突き止めて、対策工法を特定いくという思考プロセスが身につきます。
この力は補修系のどの業務をやるときにも有効活用することができるので、資格取得時だけでなく、本業においても効果を発揮し続けます。
橋梁補修工事をこなすときは、基本的には建設コンサルタントが補修設計を済ませたものが発注されてるので、その通り工事をしていくような流れになります。
コンクリート診断士にて思考プロセスを身に付けてから業務にあたると、『なぜこの補修工法が選定されるようになったのだろう?』とまず考えるようになります。
そうであれば、現場の都合で判断しなければならないときに、何の材料を選定するべきか?や、制約条件に対する落とし所について適切に判断することが出来るようになります。
ここが抜けている人は、前の現場はこうだったからなどと、論理性を欠いた感情論をぶつけてくることがありますが、正直聞くに耐えないです。
試験の論文自体の難易度から考えて、そこまで思考深くなるかと言われるとそうでもない気もしますが、試験対策をする過程で、繰り返し損傷に対する、『原因推定』、『対策』を繰り返していくうちに、業務遂行をしていく上でかけがえないものが身につきます。